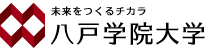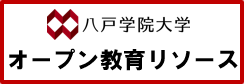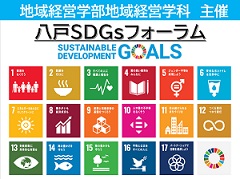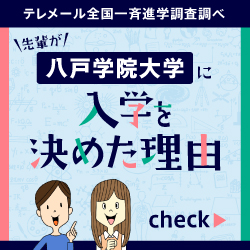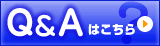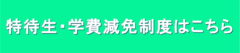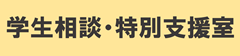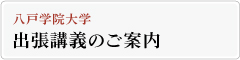カリキュラム
※カリキュラムは変更になる場合があります。
- 1年次(第1・2セメスター) 人間健康に関する基礎を広くわかりやすく学びます。
- 2年次(第3・4セメスター) 実践を通した専門的な学習が入ってきます。
- 3年次(第5・6セメスター) 進路決定の準備と卒業研究への取り組みが始まります。
- 4年次(第7・8セメスター) 進路を決定し、卒業研究を仕上げます。
※令和7年度教育課程表より
リベラルアーツ
「幅広く深い教養および総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養する」ために、総合的な思考力・判断力・問題解決能力を養うことを目的として専門教育科目と併行して、主として1年次・2年次に学修します。
導入教育
宗教学 、地域文化論、基礎演習、プレゼンテーション、情報処理基礎、データサイエンス入門、日本語表現リテラシー、言語学
外国語を学ぶ領域
英語(Ⅰ・Ⅱ)、英語コミュニケーション、英語(TOEIC)(Ⅰ・Ⅱ)、ドイツ語(Ⅰ・Ⅱ)、
韓国語、中国語
日本語を学ぶ領域
日本語(Ⅰ~Ⅵ)
人としてのあり方を学ぶ領域
哲学、芸術論、デザイン論、心の科学、行動の科学、人間関係論
社会のあり方を学ぶ領域
日本国憲法、政治学、社会学、国際関係論、海外事情
自然と科学を学ぶ領域
自然科学概論、数学、スポーツの科学、スポーツ実技(Ⅰ・Ⅱ)、防災と危機管理
日本の文化と社会を学ぶ領域
日本文化(Ⅰ・Ⅱ)、日本社会(Ⅰ・Ⅱ)
専門教育科目
こころとからだに関する健康科学の教養を深めるための学科必修科目と、医療・体育・心理・看護・福祉・環境・栄養等の幅広い分野の基礎と実践力を身につけるための選択科目を配置しています。また、現代社会の健康ニーズに対応できる能力の育成を目指して「健康管理士コース」「健康スポーツコース」「健康教育コース」「健康心理コース」「健康福祉コース」の5コースをおき、資格・免許の取得のために「健康管理士コース」には「健康管理士一般指導員」、「健康スポーツコース」には「トレーニング指導者」「スポーツコーチングリーダー」、「健康教育コース」には「教育職(保健体育)」「教育職(養護・保健・看護)」、「健康心理コース」には「認定心理士」、「健康福祉コース」には「社会福祉士」を取得可能となる過程を設けています。学生は各自の進路目標にそって各々のコースの科目を中心に選択履修します。
キャリア教育
キャリアデザイン(Ⅰ・Ⅱ)、インターンシップ(Ⅰ・Ⅱ)
専門基礎科目
健康科学総論、生命と倫理、健康栄養学、医学一般、心理学、解剖学、衛生・公衆衛生学Ⅰ
専門基幹科目
発達心理学、医学一般Ⅱ、生理学(運動生理学含む)、衛生・公衆衛生学Ⅱ、小児保健、精神保健
専門展開科目
生涯スポーツ論、ヘルスエクササイズ、健康と運動処方、栄養指導論、栄養学(食品学を含む)、人間
環境論、食生活論、学校保健(学校安全を含む)、救急処置(実習を含む)、臨床心理学、老人・障害
者の心理、介護概論、地域スポーツ論、運動と栄養、スポーツバイオメカニクス、トレーニング総論、
スポーツ心理学、コーチング論、スポーツ社会学、生涯スポーツ演習(Ⅰ・Ⅱ)、健康スポーツ実習
(Ⅰ・Ⅱ)、体育原理、運動学(運動方法学を含む)、基本実技、水泳、ダンス、陸上競技、ラグビー、
サッカー、バスケットボール、バレーボール・バドミントン、テニス、ソフトボール、武道Ⅰ(柔
道)、武道Ⅱ(剣道・弓道)、器械体操、スキー、スケート、養護概論、看護学、微生物学、免疫学、
健康相談活動の理論および方法、看護実践論、看護技術演習、看護学臨床実習(Ⅰ・Ⅱ)、薬理概論、
健康心理学、児童心理学、認知心理学、感情心理学、青年心理学、心理学研究法、社会心理学、心理統
計学(Ⅰ・Ⅱ)、心理学基礎実験、ヘルスカウンセリング、心理学実習、社会福祉の原理と政策(Ⅰ・
Ⅱ)、社会福祉調査の基礎、ソーシャルワークの基礎と専門職(Ⅰ・Ⅱ)、ソーシャルワークの理論と
方法(Ⅰ~Ⅳ)、地域福祉と包括的支援体制(Ⅰ・Ⅱ)、福祉サービスの組織と経営、社会保障(Ⅰ・
Ⅱ)、高齢者福祉、障害者福祉、児童・家庭福祉、貧困に対する支援、保健医療と福祉、権利擁護を支
える法制度、刑事司法と福祉、ソーシャルワーク演習(Ⅰ~Ⅴ)、ソーシャルワーク実習指導(Ⅰ~
Ⅲ)、ソーシャルワーク実習(Ⅰ・Ⅱ)、福祉フィールドワーク演習、福祉フィールドワーク実習、国
際社会福祉論、健康科学実習
専門研究科目
研究演習(Ⅰ~Ⅵ)、卒業研究(Ⅰ・Ⅱ)
教職教育課程
卒業に必要な科目の単位数を修得し、かつ教職に関する専門科目及び免許状授与の資格を得るために必要な科目の単位を修得することによって、卒業と同時に教員免許状が取得できます。
<取得できる免許状の種類>
中学校教諭一種免許状(保健体育)、高等学校教諭一種免許状(保健体育)、中学校教諭一種免許状(保健)、高等学校教諭一種免許状(保健)、高等学校教諭一種免許状(看護)、養護教諭一種免許状
教職に関する科目
教育原理、教職概論、教育行政、教育心理学、特別支援の理解、教育課程論、道徳教育の理論と実践、総合的な学習の時間の指導法、特別活動論、教育方法論(ICT活用含む)、生徒指導論、教育相談、進路指導論、教育実習(A・B)、養護実習、教職実践演習(中高)、教職実践演習(養)、保健体育科教育法(A~D)、看護科教育法(A・B)
講義概要
履修系統図
※各科目の特長および目標等は、「講義シラバス」でご覧いただけます。
教員免許取得までの流れ~実践編~
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
| 高等学校教諭一種 保健体育 保健 看護 |
教職課程履修届 | 教育実習先決定 | 教育実習事前指導 ↓ 教育実習 ↓ 教育実習事後指導 |
|
| 中学校教諭一種 保健体育 保健 |
介護等体験 特別支援学校 (2日間) 社会福祉施設 (5日間) |
|||
| 養護教諭一種 | 養護実習先決定 看護学臨床実習Ⅰ (2週間) 看護学臨床実習Ⅱ (2週間) |
養護実習事前指導 ↓ 養護実習 ↓ 養護実習事後指導 |
※教職課程履修者は履修初年度に別途履修料を納入しなければなりません。