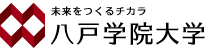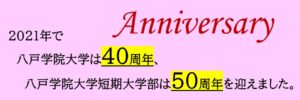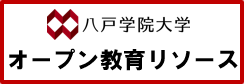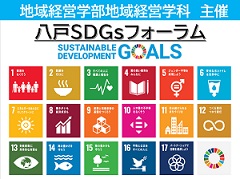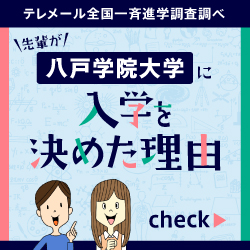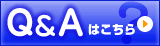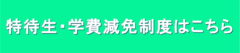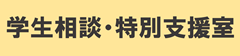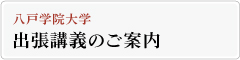髙須 則行
2023年04月01日現在
| 氏名 | 髙須 則行(タカス ノリユキ/Noriyuki TAKASU) |
| 所属/職位 | 八戸学院大学 地域経営学部 地域経営学科/教授 |
| 最終学歴/学位 | 日本大学大学院法学研究科博士後期課程公法学専攻 満期退学 |
| 主な経歴 |
1993年11月 国士舘大学法学部非常勤講師(1994年03月まで) 2001年07月 日本大学通信教育部非常勤講師 2002年04月 横浜商科大学非常勤講師(2010年03月まで) 2003年04月 日本大学法学部非常勤講師(2016年03月まで) 2003年05月 明治学院大学法学部非常勤講師(2006年03月まで) 2005年04月 獨協大学法学部非常勤講師(2006年03月まで) 2005年04月 東海大学法学部非常勤講師(2016年03月まで) 2006年04月 日本大学商学部非常勤講師(2016年03月まで) 2007年04月 日本大学工学部非常勤講師(2012年03月まで) 2010年04月 日本大学経済学部非常勤講師(2016年03月まで) 2010年09月 税務大学校非常勤講師(2015年09月まで) 2012年04月 立教大学兼任講師(2016年03月まで) 2012年04月 東洋大学法科大学院非常勤講師(2016年03月まで) 2014年04月 日本大学薬学部非常勤講師(2016年03月まで) 2015年04月 獨協大学法学部非常勤講師(2016年03月まで) 2016年04月 八戸学院大学 ビジネス学部 ビジネス学科 准教授 2019年04月 八戸学院大学 地域経営学部 地域経営学科 教授 現在に至る |
| 主な所属学会 | 日本法哲学会 |
| 連絡先 | TEL:0178-25-2711(大学) FAX:0178-25-2729(大学) E-mail n-takasu@hachinohe-u.ac.jp |
| 専門分野 | 法哲学 |
| 研究テーマ | 20世紀ドイツ法学方法論 |
| 担当科目 | 法学概論、民法、商事法、行政法、日本国憲法、基礎演習、プレゼンテーション、研究演習Ⅰ~Ⅵ |
主な研究業績
| 区分 | 著書、学術論文等の名称 | 単/共 | 発行・発表年月 | 発行所、発表雑誌・学会等 |
| 著書 | 『法学[第3版]』 | 共 | 2020年03月 | 弘文堂 |
| 著書 | 『アプローチ法学入門』 | 共 | 2017年02月 | 弘文堂 |
| 著書 | 『法学[第2版]』 | 共 | 2017年01月 | 弘文堂 |
| 著書 | 『法学』 | 共 | 2015年02月 | 弘文堂 |
| 著書 | 『新法学入門〔第2版〕』 | 共 | 2002年12月 | 弘文堂 |
| 著書 | 『法学マテリアルズ』 | 共 | 2009年06月 | 八千代出版 |
| 著書 | 『プライマリー法学』 | 共 | 2008年05月 | 芦書房 |
| 著書 | 『新法学入門』 | 共 | 2004年04月 | 弘文堂 |
| 研究ノート | 「フィリップ・ヘック『利益法学』(下)」 | 単 | 2018年12月 | 八戸学院大学紀要第57号31頁~41頁。 |
| 研究ノート | 「フィリップ・ヘック『利益法学』(上)」 | 単 | 2018年3月 | 八戸学院大学紀要第56号49頁~59頁。 |
| 研究ノート | 「ドイツ法律家新聞におけるゾームとヘックの『概念法学』に関する3つの小論文」 | 単 | 2016年12月 | 八戸学院大学紀要第53号11頁~22頁。 |
| 論文 | 「イェ―リングの法律学方法論について―イェーリングの法有機体説との関連において―」 | 単 | 2011年03月 | 日本大学法学紀要第52巻 |
| 論文 | 「イェーリングの法学観について-構成法学としての概念法学-」 | 単 | 2004年11月 | 法哲学年報(2003) |
| 論文 | イェーリングの法学観について-イェーリング著『法律学は学問か?』を中心に | 単 | 2003年03月 | 日本法学第68巻第4号 |
| 論文 | 「カントロヴィッツの自由法運動に対する批判について」 | 単 | 2003年03月 | 佐野短期大学研究紀要第14号 |
| 論文 | 「イェーリングの『転向』問題」 | 単 | 2001年03月 | 日本大学法学紀要第42巻 |
| 論文 | 「パンデクテン法学における法の欠缺と類推」 | 単 | 1995年03月 | 日本大学法学紀要第36巻 |
| 論文 | 「カントロヴィッツの法学論-『概念法学のための戦い』から」 | 単 | 1987年09月 | 日本大学大学院法学研究年報第17号 |
| 翻訳 | イェーリング著「売買契約における危険についての理論に関する論考 Ⅱ 」(下)・(中・二)・(中・一)・(上) | 共 |
2015年09月・ 2015年03月・ 2013年09月・ 2011年11月 |
東海法学第50号 東海法学第49号 東海法学第47号 東海法学第45号 |
| 翻訳 | イェーリング著「売買契約における危険についての理論に関する論考」(下)・(上) | 共 |
2010年03月 2009年09月 |
東海法学第43号 東海法学第42号 |
| 翻訳 | イェーリング著「物を給付すべき者は、それによって生み出された利益をどの程度引き渡さなければならないか?」(下)・ (中)・ (上) | 共 |
2009年02月 2005年12月 2003年03月 |
東海法学第41号 東海法学第34号 東海法学第29号 |
| 翻訳 | イェーリング著「法律学は学問か?」 | 共 | 2003年12月 | 東海法学第30号 |
| 翻訳 | イェーリング著「今日の法律学に関する親展の書簡――差出人氏名不詳――」(四・完)・(三)・(二)・(一) | 共 |
2001年03月 2000年03月 1999年07月 1999年03月 |
東海法学第25号 東海法学第23号 東海法学第22号 東海法学第21号 |
| 翻訳 | イェーリング著「再び現世にて――事態はどのように改善されるべきか――」(下)・(上) | 共 |
1998年03月 1997年08月 |
東海法学第19号 東海法学第18号 |
| 翻訳 | イェーリング著「法学者の概念天国にて――白昼夢――」(下)・(中)・(上) | 共 |
1997年03月 1996年08月 1996年03月 |
東海法学第17号 東海法学第16号 東海法学第15号 |
| 翻訳 | イェーリング著「フリードリッヒ・カール・フォン・サヴィニー」 | 共 | 1993年03月 | 東海法学第19号 |
| 報告 | イェーリングの「法学観」について | 単 | 2003年11月 | 日本法哲学会(2003年度) ・法政大学 |
| 報告 | 法的思考におけるアナロジーの意義 | 単 | 1996年12月 | 日本大学哲学会・日本大学 |
最近の研究業績
| 区分 | 著書、学術論文等の名称 | 単/共 | 発行・発表年月 | 発行所、発表雑誌・学会等 |
| 著書 | 『法学[第3版]』 | 共 | 2020年03月 | 弘文堂 |
| 著書 | 『アプローチ法学入門』 | 共 | 2017年02月 | 弘文堂 |
| 論文 | 『権利のための闘争』のために | 単 | 2022年12月 |
日本評論社『法学セミナー』 2022年12月 |
| 研究ノート | 髙須則行訳 フィリップ・ヘック著「法の基礎」(下) | 単 | 2021年03月 | 八戸学院大学紀要第62号1頁~6頁 |
| 研究ノート | 髙須則行訳 フィリップ・ヘック著「法の基礎」(上) | 単 | 2020年12月 | 八戸学院大学紀要第61号1頁~10頁 |
| 研究ノート | 髙須則行訳「フィリップ・ヘック『利益法学』(下)」 | 単 | 2018年12月 | 八戸学院大学紀要第57号31頁~41頁。 |
| 研究ノート | 髙須則行訳「フィリップ・ヘック『利益法学』(上)」 | 単 | 2018年03月 | 八戸学院大学紀要第56号49頁~59頁。 |
| 研究ノート | 「我が国の成年後見制度の概要-市民後見人の在り方を検討する前提として-」 | 単 | 2018年03月 | 産業文化研究第27号55頁~66頁。 |
| 研究ノート | 髙須則行訳「ドイツ法律家新聞におけるゾームとヘックの『概念法学』に関する3つの小論文」 | 単 | 2016年12月 | 八戸学院大学紀要第53号11頁~22頁。 |
| 報告書 | 成年後見人の身上監護事務について | 単 | 2019年3月 | 産業文化研究第28号59頁~62頁。 |
主な社会活動
| 項目 | 期間 |
| 八戸市市民後見推進協議会委員 | 2016年5月1日~現在 |
| おいらせ町総合計画審議委員 | 2022年8月4日~2024年8月3日 |
自己紹介
遺跡・神社・仏閣を訪ねるのを趣味にしています。是川縄文館の国宝「合唱土偶」、櫛引八幡宮の国宝赤糸威鎧「菊一文字」・国宝白糸威褄取鎧等を見に行けることにワクワクしています。